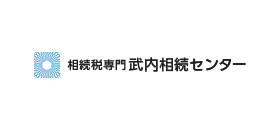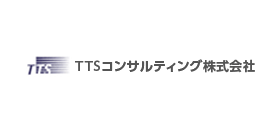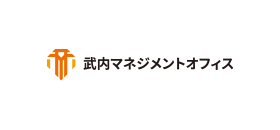平成27年に相続税が改正されて、早11ヶ月が経過しました。
今回の改正で基礎控除が大幅に引き下げられたということは皆さんご存知かとは思いますが、そもそも相続とは何か、誰が相続人となるのか?「相続」と「遺贈」の違いとは?ということについてご説明していきたいと思います。
そもそも相続とは民法上の領域で、ある人(この方を「被相続人」と言います。)が死亡したとき、その被相続人の財産を一定範囲の親族に受け継がせることです。
財産には、預貯金や有価証券をはじめ不動産などのプラスの財産はもちろん、借入金やまだ納めていない税金といったマイナスの財産も含まれることになります。
そして相続人は誰になるのかということですが、民法上において相続人になれる人(「法定相続人」)は配偶者、子(いわゆる「直系卑属」)、両親(いわゆる「直系尊属」)、兄弟姉妹などに限られ、その順位も民法で定められています。
配偶者は無条件で相続人となり、配偶者以外は次の順位によります。
第1位順位…直系卑属。(子またはその代襲相続人。)
第2位順位…直系尊属。(父母や祖父母。)
第3位順位…兄弟姉妹。
また、「相続」と混同しやすい用語として「遺贈」というものがありますが、相続とは、なんら手続きを経ることなく当然に、被相続人の財産が相続人に引継がれることを指すのに対し、遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。
ちなみに一般的に遺言書では相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対しても遺贈することはできます。
いかがだったでしょうか。相続は手続が難しい上に、それらで悩んでいる間に、各種手続の期限が迫ってしまう、さらには事態が悪化する恐れもあります。
監修:税理士法人武内総合会計